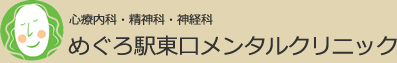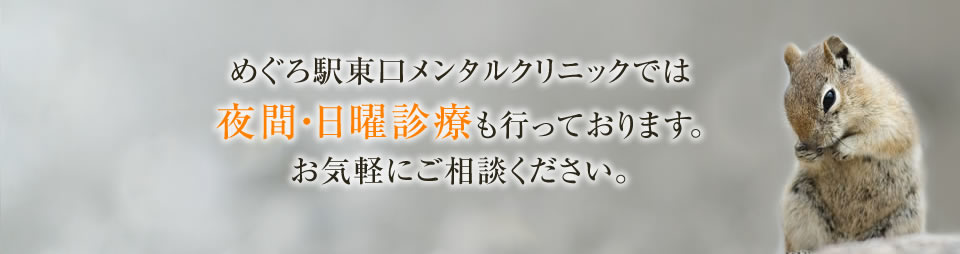
- トップ
- 病気の症状・診療の方針一覧
- 病気の症状・診療の方針
- 操作的診断基準を用いた、うつ病の診断
操作的診断基準を用いた、うつ病の診断
うつ病の診断に用いることが出来る客観的指標は未だ存在していない。このため、初診時に表出されている症状だけでなく、問診の場でできるだけ多くの情報を集め総合的に判断し、後の経過をも勘案して最終診断がなされるのである。
最低必要な情報として、
過去の身体的な病気も含めた治療歴。
精神疾患の家族がいないかどうか。
子供の頃の発育の状態と生活史、両親を中心とした家族関係
学歴・職歴
家族構成と家族仲
自分の自覚している性格傾向
病気の前の社会での適応状態
対人緊張の強さ(子供の頃から今までの、人見知りの度合い)
睡眠の状態
仕事の内容とその量
休養日の取り方、過ごし方
などがあげられる。
操作的診断基準を用いたうつ病の診断で一番重要なことは、診断基準(ここでは最新の診断基準であるDSMⅤを指す)の中で示される、次の2項である。
1、その人自身の言葉か、他社の観察によって示される、ほとんど1日中、ほとんど毎日の抑うつ気分
2、ほとんど1日中、ほとんど毎日の、すべて、またはほとんどすべての活動における興味または喜びの減退。
ここで重要なことは
①抑うつ気分、もしくは活動における興味または喜びの減退は、ほとんどの時間でみられることである。休日などでストレス負荷が減ることで症状が無くなるような状態は、うつ病とは診断しないという事である。このことは、うつ病が環境因やストレスの負荷が原因で発病したとしても、一度発病すると病気(個体の機能不全)であり、環境への反応では無いということを示唆しているという意味で重要である。環境因で症状の変化はあるものの、症状自体は個体に起因する機能不全のため確実に持続するのである。
②もう一つ重要な点として、不安という感情が診断基準では重視されていないということである。このことは、ストレス環境下にあるうつ病患者が不安焦燥感を感じ、時には中心的な訴えとなることを考えると、一見矛盾するような事項である。しかし、多くの精神科医が経験しているように、休職や入院などでストレス負荷が少なくなった際には意欲低下・抑うつ気分・興味の減退などがほとんど変化することない時期でも、不安は見られなくなることが多い。また、不安を重視した場合、適応障害との混同が危惧さえることも無視はできない。このような混乱を避けるため、診断基準は不安をうつ病状態にある患者のストレスへの受容力の低下を示しているだけで、うつ病の本体とは捉えられていないものと私は推測している。このことは、大脳生理学的な所見からも、不安をつかさどる中枢である偏桃体の活動性はむしろ落ちているという報告が多いことからも裏付けられている。
重症であれば比較的診断は容易なのであるが、軽症例では難しい面も少なくない。
このような場合に最近注目されているのが、はっきりとした意欲低下や抑うつ気分が現れる前から、記憶力を中心とした認知機能の低下がみられるという報告が多くなっている点である。実臨床の場でも、仕事は何とかできている程度の軽症例でも、「頭の回転の悪さ」「記銘力の低下」「ミスの増加」が見られることがある。ただ、このような所見は不安焦燥感が強まる状態でも、集中力の低下の二次的な問題点として出てくる可能性のある症状である。不安焦燥感が中心であれば、うつ病ではなく不安障害(特に適応障害)を考える必要がある。
このような場合は、自由に過ごせる時期(用事の無い休日等)の活動性を詳細に問診することでうつ病の可能性を探ることが可能となる場合もある。この際に重要なのは、過去の行動パターンと性格の聴取である。絶対的な活動量より、過去の行動パターンと変化している場合に注意が必要である。
うつ病の診断に、補助的に用いられる項目として、次の事項があげられている。下記項目は、すべてほとんど毎日見られる必要がある。
不眠または過眠
精神運動焦燥または制止
疲労感、または気力の減退
無価値観、または過剰であるか不適切な罪業感
思考力や集中力の減退、または決断困難
この中では、正常な悲観・落ち込みとの鑑別において、「無価値観、または過剰であるか不適切な罪業感」は重要であろう。正常な反応では見られにくい状態であるからである。しかし、診断基準も示すように、この感情はあくまでも補助的因子に過ぎないことも注意し、診断の過剰を招かないようにすることも肝要である。
今回死別反応はうつ病の診断基準を満たしても、うつ病とは診断しないという、例外規定が撤廃された。これは、死別によるストレスからも十分うつ病が発生しうるため、過小診断を防ぐ目的ではあるが、過剰診断を減らす目的から外されていた死別反応が除外規定を外されたことは、正常の悲観・落ち込みと、うつ病を鑑別するうえでより慎重な態度が精神科医に要求されることとなってしまった。
このことへの対応として、DSMは以下の点を慎重に見て行くことを推奨している。
①うつ病の抑うつは持続的であり、1日のほとんどの時間続き、最低2週間以上持続する。
②うつ病の抑うつは特定の考えや関心ごとに結びつかない傾向があり、正常な悲観は個々人の経験や関心・悲観の原因になった事項に関連しつつ、個々人の経験や個性に彩られた個性的な内容を持つことが多い。
③うつ病の抑うつは、自己批判や無価値観が伴いやすいが、正常な悲観では自己評価は保たれることが多い。ただ、過去の後悔が強い場合には、例外もありうる。
④うつ病の抑うつには、死についての考えが付き、自分の命を終わらせることに焦点が当たる場合も少なくないが、正常な悲観ではそのような場合は例外的である。
鑑別診断
うつ病の診断を行う上で、以下の2つの疾病の鑑別は重要である。
双極性(感情)障害(いわゆる躁うつ病)、適応障害、持続性抑うつ障害(気分変調症・ディスチミア)
1、双極性障害との鑑別
双極性障害のうつ状態とうつ病の病像は酷似しており、病像だけでの鑑別は不可能に近いと言って良いものである。さらに、双極性障害の2型ではうつ病相が9割近くを占め、このせいで双極性障害の診断が正確になされるまで、実に7年物年月がかかるという報告がある。
この為、過去の生活史や家族の精神病者の有無、病状の水位の慎重な観察が必要となる。さらに、下記が診断における双極性障害を疑わせる補助情報として重要視されている。
①過眠
②食欲増進
③精神運動性の抑制
④精神病症状の合併
⑤気分の不安定さ
⑥若年発症(25歳以下)
⑦うつ病相の再発の多さ(5回以上)
⑧身体的愁訴の少なさ
⑨うつ病相の罹病期間が短い(6か月以下)
日本では双極性障害がうつ病と考えられている例が多いと統計的な知見から推測され、この反省もあり最近は双極性障害を積極的に診断してゆこうという医師が増えてきている。このてめ、あきらかに過剰診断と思われるような症例が見られ始めていることも事実である。うつ病と双極性障害では、事項に示すように薬物療法では大きな違いがあり、また双極性障害では長期にわたって感情安定剤を服用する必要がある。しかし、感情安定剤は他の薬と比較しても副作用は多く、妊娠毒性も強いものが多い。双極性障害が若年発症であることを考えると、この副作用は患者さんの人生に大きな問題をきたしかねない。この為、当院においては、そう状態を明確に確認しない限り、うつ病として治療を行い危険因子が多いなど双極性障害の可能性が高い症例においては、経過を慎重に観察してゆくにとどめている。おおむね6か月を経てもうつ病が寛解しない症例において、初めて双極性障害の治療を始める方針を持っている。
なお近年において、別項に記載するうつ病と双極性障害を鑑別する、客観的な検査法が実用化(光トポグラフィー)や研究(血小板内カルシウム濃度等)されており、十分とまでは言えないが診断の正確性を上げる手段が増えつつある。将来の科学の発展に期待である。
2、適応障害との鑑別
適応障害の診断基準は、要約すれば下記のようになる。
①はっきりとしたストレス因があり、そのストレス因から3か月以内に発症する。
②そのストレス因への反応が、一般的な常識から考えて過剰と思える程度であること。
(上司にしつこく苦言を呈されることが続くことで、会社に行こうとするだけで足が震え息苦しくなり、出社できなくなってしまうほど強い不安反応が出ている場合などは、多くの人は嫌だと感じるが休むまでは至らず反応は過剰と考えられる。)
③社会的、職業的、または他の重要な領域において機能に重大な障害が見られていること。
④そのストレス因、またはその結果がひとたび終結すると、症状が6か月以内に収まること。
⑤他の精神疾患の基準を満たしていない。また、他の精神疾患の単なる悪化でもない。
いかがでしょうか?適応障害の診断基準は非常にあいまいであると言わざるを得ない。⑤から分かるように、除外診断が中心となる。つまりうつ病が存在すると、適応障害は診断できず、うつ病と適応障害の合併という診断はしないでおこうという約束事でしかない。
③は病気と考える上において必要条件であり、適応障害において特別な基準ではない。
④は終わってみないと分からず、診断を行う上においては意味のない基準である。最終的に、どうだったかの基準でしかない。
単にはっきりしたストレス因から、社会的機能等が低下した状態を指すのである。
ただ、適応障害という状態は非常に多く、うつ病とは違った対応が必要な状態であるがゆえに、きちっとした鑑別が必要と考えている。
この為当院では、従来型診断や心理学的知見、生物学的知見から下記のような条件を捕捉し、適応障害として考えるようにしている。ただ、これは診断基準に矛盾した内容を含むものではなく、診断基準のあいまいさを補正しているに過ぎない。
a. 1、その人自身の言葉か、他者の観察によって示される抑うつ気分を認める場合も、ほとんど1日中ほとんど毎日では無い。
b.すべて、またはほとんどすべての活動における興味または喜びの減退を示す場合も、ほとんど1日中ほとんど毎日では無い。
c.不安を主たる症状として認め、ストレス因に暴露されない場合に、症状は消退するか少なくとも軽快する。
d.ストレスに反応して出現する症状は、自分で制御できる程度を超えている。
a.b.は、うつ病の診断基準を満たさないという診断基準の要求に基づいて定義されている。
除外基準であるため、上記項目は必須であるが、抑うつや喜びの減退は適応障害の主たる状態像を指摘したものではない。適応障害において、抑うつや喜びの減退は、ストレス因に暴露された時もしくは想起したときに出現する不安感の影響によって二次的に出現すると捉えるべきである。
c.は私が適応障害を診断する上においては最も重視することであり、うつ病との鑑別にも重要である。うつ病は脳の何らかの機能不全の持続であるため、中心の症状(抑うつ・喜びの減退)は環境因に影響を受けることはあるが大きくは左右されず持続するものである。職場でのストレスにおける適応障害にいては、休日には改善することが普通である。改善が見られず、かつ休日の活動性の低下や喜びの減退がはっきりしている場合は、うつ病を疑うべき所見である。
また、今回の改正まで、適応障害は不安障害に分類されていたことや、心理学的な不安記憶からの自制できない不安反応が主な特徴と私はとらえているため、不安を主とした症状を呈する疾病ということを表している。ストレス体験が海馬に体験記憶として記録され、体験記憶の内容に即して偏桃体の過敏性を高め、自制できない不安反応をもたらしている状態と推論している。大脳辺縁系を中心とした反応のため、自覚した不安ではなく本人も制御の方法に戸惑っている状態ととらえている。
ストレス反応が自制できる程度のものであれば、上記診断基準③を示さないため、病気とは診断することは慎重にするべきである。
めぐろ駅東口メンタルクリニック
〒141-0021
東京都品川区上大崎3-3-1
オバタビル5F
Tel:03-6277-2188